![]() 千葉大学園芸学部-微気象学-
千葉大学園芸学部-微気象学-
“微気象学”のタイトルで今年限りの集中講義を担当することになりました。ただし、ピンチヒッターですので中身は“水文学”です。その中に、微気象学の必須の教育目標としてペンマン・モンティース式の理解を依頼されていますので、そこはしっかりやります。
従来の科学、いわゆる西洋近代科学では対象を要素に分割し、要素ごとに探究し、全体をシステムとして結合するという方法がとられることが多いようです。要素として重要でないとされたものは棄却されます。しかし、人間の作用も含む現実世界における現象はどうでしょう。あらゆる要素(要因)が事象の出現に関わっています。要素の数はそれこそ無限にあるのです。事象に対する要素の重要性も場所や時間によって異なるでしょう。システムというよりも大小様々な要素が容れ物(これが環境)の中で押し合いへし合いしながら反応するというイメージがあります。この要素には自然だけではなく人間的側面をも含みます。
園芸学の対象である作物も、普遍的な(時間、位置によって変わらないということ)場所で育つわけではありません(植物工場はちょっと違うかも知れませんが)。このような対象を理解するためには、普遍性探究というよりも関係性を探究する姿勢が重要だと思います(普遍性探究型科学と関係性探究型科学)。関係性探究型科学では事象の全体性を俯瞰する見方が大切になります。俯瞰とは関係性を構成する要素の見極めですね。
微気象学の扱う現象も含まれる水循環も場の条件、時間によって異なった現れ方をします。このような事象を理解するために、講義では素過程の話をしながらも様々な事象を取り上げ、関連性を探究したいと思います。いわゆる脱線というやつです。講義を通してみなさんが自身の自然観を確立することができれば成功としたいと思います。
シラバスを決めてその通りに講義を行うやり方は普遍性探究型科学、あるいは要素分割型、機械論的な方法論に適しています。関係性探究型科学では様々な事象との関係性をあちこちに飛んで探究します。そこでは教員と学生の一時限りの化学反応のようなものが生じるのではないか。それが身につくということです。日本では学ぼうと思えば優れた参考書は十分手に入ります(途上国ではないのだから)。最近ではネット上の文献データベースも充実してきました。
大学で学ぶべきことは、既成の知識というよりも、現実世界のありさまを理解することだと思います。現実世界は異なる階層を持つ様々な関係性から成り立っています。関係性を追求することが“真理の探究”でもあると思います。それは仏教の自然観でもあります。この精神的習慣が身につくと、社会における様々な問題、課題に自律的に取り組むことができるのではないかな。
集中講義は地獄でもありますが、関係性を楽しむことができればおもしろくなるかも知れません。
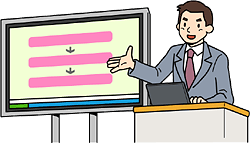 講義資料
講義資料
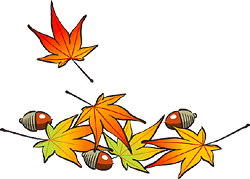 追加資料
追加資料
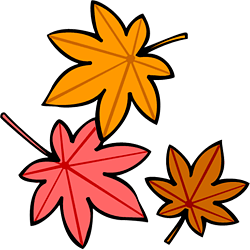 参考
参考