担当:近藤昭彦
はじめに
半年間「自然地理学Ⅰ」を担当します。よろしくお願いします。地理学は数学や物理学とはちょっと違います。原理や法則がわかれば解ける問題ではなく、地理学の対象、すなわちこの世界そのものを総合的に、俯瞰的に観察し、様々な要素の関係性を見つけ出すことによって、この世界のありさまを理解しようとする学問の領域です。自然地理学では“自然”に軸足を置きますが、人文地理学の領域とも関わり、環境(人・自然・社会が相互作用する範囲)や災害(人と自然の関係性に問題が生じた事象)の本質を理解しようとします。ちょっと難しいと感じるかも知れませんが、みなさんの視野を広げ、様々な視座を獲得することによって、生きる力を獲得することができるでしょう。
2022年度から高校で「地理総合」が必履修化されています。それは、厳しい社会情勢の中で暮らしていくためには地理学の知識、経験が必要であることが認識されたということでもあります。地理学を通して、みなさんが生きていく社会がどうなれば良いのか、考えてください。答えはひとつではありません。唯一の正しい答えを探す、という過去の習慣から脱して、自分で諒解できる答えを見つけて、異なる考え方の人々とも対話しながら未来を創っていくことができる“ひと”になってほしいと思います。
教科書は古今書院「みわたす・つなげる自然地理学」を使います。これは地理総合に対応した新しい教科書で、人文系の事象、地域の事象との関係性も学べるように配慮されています。同じシリーズの「みわたす・つなげる人文地理学」と「みわたす・つなげる地誌学」も購入して読んでいただけると理解が進むと思います。後期は「みわたす・つなげる人文地理学」を使って、人文系の諸事象と自然の関係性を学びます。これまで使っていた「風景のなかの自然地理」は再版停止になってしまいましたが、講義資料の中で活用していきます。このWEBページを参照してください。
教科書では前期15回の講義に対応した章立てになっています。シラバスもこの章立てにしたがって作成してありますが、シラバス通りには進まないかもしれません。それは、地理学が関係性探求型科学だから。学科としての数学や物理は一般性探求型科学、あるいは普遍性探求型科学と呼ぶことができます。それは答は一つだから。でも、地理学が探求する人・自然・社会のよりよい関係性には様々な選択肢があります。すなわち、様々な未来の選択があり、それはみなさんが決めていかなければなりません。競争をして進歩をめざす社会がよいのか、いろいろな人や国、地域が協調して暮らすことができる社会が良いのか、対話を通じて諒解していく必要があります。世の中は対話をせずに、戦争、闘争、支配に向かうことが多いように感じますが、対話をして諒解できる社会こそ、めざすべき社会ではないかと思います。地理学を通じて世の中を総合的、包括的、俯瞰的に眺める習慣を身につけてください。それが対話につながります。講義では関係性を追求して脱線することが多いと思います。シラバス通りには行かないかもしれませんが、そのために教科書があります。講義と教科書の双方を活用してください。講義の内容はこのホームページで補足していきます。
【2025年度追記】今、学術(科学)のあり方が政治の力によって変わろうとしています。学術会議法案が採択されると日本の未来が変わるかも知れません。私は科学には①基礎科学(好奇心駆動型科学)、②課題解決型科学(使命達成型科学)と③問題解決型科学、があると思います。この3つの科学の関係を良好に保つことが日本の未来を創り出すと考えていますが、詳しくは教室で話したいと思います.地理学のあり方とも大きく関係します。
まず、教科書「みわたす・つなげる自然地理学」の「はじめに」と第1章をじっくり読んでください。上記の資料は一昨年度まで使った資料ですが、自然地理学の特徴について理解を深めることができると思います。
地理学を理解する要は、この世の中は様々な関係性によって成り立っていること、その関係性は地域や時代によって異なっていること、を理解することだと思います。物理学や数学は普遍的な原理がわかれば、問題を解くことができますが、地理学が扱う対象は地域の特徴、それは自然の特徴だけでなく、人間的側面の特徴も含んだ地域性を認識することによって理解できるものです。なかなか大変だと感じるかもしれませんが、それで初めて“問題”を理解し、解くことができるようになります。みなさんがこれから対峙しなければならないのは、答えがない、あるいは答えが一つではない問題です。人生の中で自分が進む方向に対して、いかに諒解を形成することができるのか、地理学がヒントを与えてくれるでしょう。
地理学では様々な地図を使って地域の理解を深めます。WEBで使えるページが充実していますので、紹介します。活用してください。たくさんありますが、少しずつ追加していきます。
様々な主題図を画面上で重ねて表示できます。国土地理院では主題図情報、災害情報や、地理学教育支援サイトが充実していますので参考にしてください。
旧版地形図(明治以降に作成された地形図で、改訂によって旧版となった地形図)と現在の地形図を並べて表示できます。過去の土地利用は土地の性質を表し,災害を予見することができます。
自治体に作成が義務づけられているハザードマップのポータルサイトです。「重ねるハザードマップ」は情報量が豊富になってきました。
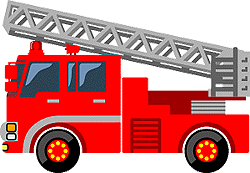 災害は地理学の主要な対象の一つです。なぜなら、災害は地域における人と自然の関係性に生じた問題ということができるからです。2024年1月1日能登半島地震が発生しました。能登半島から遠く離れた千葉県でも、それはひとごとではありません。能登半島地震に伴って発生したハザード(災害を引き起こす自然現象)は千葉県でも履歴があるものばかりでした。下記の講演資料を参考にしてください。<教科書、第13章、第15章と関連>。
災害は地理学の主要な対象の一つです。なぜなら、災害は地域における人と自然の関係性に生じた問題ということができるからです。2024年1月1日能登半島地震が発生しました。能登半島から遠く離れた千葉県でも、それはひとごとではありません。能登半島地震に伴って発生したハザード(災害を引き起こす自然現象)は千葉県でも履歴があるものばかりでした。下記の講演資料を参考にしてください。<教科書、第13章、第15章と関連>。
![]() 要点
要点
![]() 補足説明
補足説明
以下の資料は昨年度まで使っていた資料です。勉強に役立ててください。参考講義資料(PDF)
![]() 流域治水に関する情報
流域治水に関する情報
6月14日オンデマンド講義の課題(2023年度の課題ですが、2024年度も考えてみましょう)
(2023年)6月14日はオンデマンド講義とします。まず、教科書の7章をよく読んでください。最後の51ページのコラムは「気候システムと地球温暖化」ですが、気候変動の時代になり、従来の静的な気候の定義では変動に対応することができなくなったことを解説しています。多様な要因とその変化がシステムとしての気候を変えているのですが、その要因には私たちの暮らしのあり方も大いに関わっています。グローバルスケールの漠然とした変化だけではなく、地域ごとの小さな変化の積み重ねが気候を変えることもあります。
では、私たちのどのような営みが気候を変えるのでしょうか。その事例を考えて、レポートしてください。21日以降の講義でアクティブラーニング形式で講評したいと思います。
提出方法: 20日までに kondoh(at)faculty.chiba-u.jp あるいはKCNにメールで提出してください。メールベタでも添付でも結構ですが、名前は明記してください。なお、件名に【自然地理学】と入れてください。受信したら確認の返信をします。
【最終回】地域で安心して暮らすための災害の知識(7月26日)
6月に日本老年看護学会でオンデマンド講演を行ったときの資料です。これをベースにして夏休み前最後の講義を行います。講義と下記のページを参考にして自然災害について学んでください。
これは2022年度まで開講していた「災害地理学」のページです。自然災害に関して事例を通して学びます。講義資料を読み込んでください。最近、災害がたくさん発生しています。減災、防災を達成するには自らハザード(災害を起こす可能性のある自然現象)について学ぶ必要があります.わからない点は近藤まで質問してください。
![]() 新たに講義資料を作成しています。初年度は不完全な部分もありましたが、少しずつ改善していく予定ですので、ご容赦ください。
新たに講義資料を作成しています。初年度は不完全な部分もありましたが、少しずつ改善していく予定ですので、ご容赦ください。