
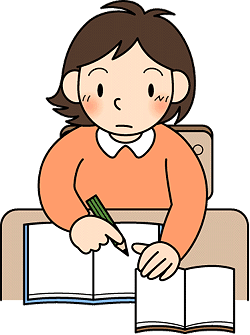 2024年度後期「自然地理学Ⅱ」レポート
2024年度後期「自然地理学Ⅱ」レポート担当:近藤昭彦
はじめに
地理学では「人文地理学」、「自然地理学」をあわせたものが「系統地理学」となります。地図学、地理学史とあわせた全体が「地理学」です。人文地理学と自然地理学ではそれぞれ扱う範囲も異なりますが、実はずべて関係しています。地理学の対象はこの世の中の全ての事象であり、あらゆる事象は様々な要因が絡み合って出現し、時には“問題”として社会のなかに顕れます。様々な要因と関係性を見通す眼こそ、現在を理解し、未来を展望することができる力の源です。
この講義では“脱線”を旨とします。脱線といっても、線路から外れてしまうわけではなく、様々な関係性の支線があることをみなさんに伝えるための脱線です。シラバスで内容が決められ、教科書に沿ってシラバス通りに進めていく講義は、実は高校までのやり方です。多様な世界を理解するためには、様々な関係性を見抜く力が必要ですが、関係性全てを講義で語り尽くすことはできません。むしろ毎回の講義における一回限りの思いつきを話すかもしれません。でも、学生諸君は関係性を発見する楽しさ、重要性に気づいてほしいと思います。
教科書は古今書院「みわたす・つなげる人文地理学」を使います。これは前期に使った「みわたす・つなげる自然地理学」とペアになっており、相互参照できますので、活用してください。教科書には指定していませんが「みわたす・つなげる地誌学」も購入して読んでいただけると理解が進むと思います。

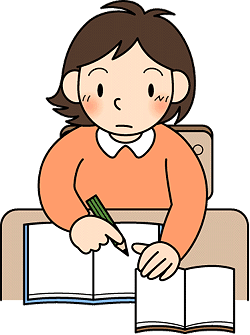 2024年度後期「自然地理学Ⅱ」レポート
2024年度後期「自然地理学Ⅱ」レポート
敬愛大学が立地する千葉県北西部は東京大都市圏とその周辺の郊外を含み、20世紀後半の高度成長期には大きく発展し、その変貌も大きな地域でした。21世紀も1/4が過ぎた現在、人口減少、少子高齢化、低成長の時代を迎え、様々な問題が顕在化してきています。千葉県の将来のあり方を“わがこと化”して考える必要があります。
①現在の千葉県北西部(東京大都市圏とその周辺部)の現状において問題だと考える事象を記述してください。
②未来(2050年を基準に考えましょう)における千葉県北西部の望ましいあり方について(地理学的観点に基づいて)、みなさんの考え方を記述してください。
提出期限:2月4日(火)
提 出 先:kondoh@faculty.chiba-u.jp(半角にしてください)まで添付ファイルで
注)必ず名前、学籍番号を記入してください。表紙はいりません。また、件名に【自然地理】と記載してください。
![]() コメント
コメント
届いたレポートをもとにしてコメントを書きたいと思います。ただし、知識の伝達が目的ではありません。現場に深く入り込み、問題を明確にし、問題の背後を探り、未来を展望する練習にしてください。答えはひとつではありません。複雑な現実に対峙し、どんな未来を構築したいのか、という若者の意思を明確にして、そのための策、それは折り合い、諒解かもしれませんが、策を練ることの練習です。
人口が減少すると「人口オーナス」といって、経済成長を阻害する要因になるといわれています。ここで、本当にそうかな?と疑問を持つことが大切です。科学技術の進歩、知識・経験の蓄積とオープン化といった流れは確実にあります。これらを活かすことのできる地域計画を立てることはわくわくするチャレンジです。言説にとらわれず、新たな方法を考える精神的習慣を身につけてみませんか。
確かに少子高齢化は現代社会における大問題ですね。特に高齢化は介護や医療のニーズを高めますが、サービスの供給が追いつかなくなっているようです。いろいろな考え方がありますが、結婚した男女がもうけるこどもの数は実は減っていません。未婚の若者が増えているのです。個人の価値観にも関わりますが、安心して結婚できる社会はどのようにして構築できるか、考えてみませんか。
高齢化も大きな問題ですが、何が問題なのでしょうか。北欧諸国では寝たきり老人はいないそうです。それは生きることの尊厳に対する考え方が社会で共有されているからだと思います。存命のための医療のあり方も考えなければなりませんね。都市の老人問題は動かない老人問題だという人もいます。高齢者が身体を動かし、健康を保つことのできる社会とはどんなものか、地理学的観点(空間と時間軸)で考えましょう。あなたも老人になります。過ぎてしまえばあっという間ですよ。
全ての世代がもっと交流、対話できれば分断を解消し、よりよい社会形成に向けて進むことができるのではないかな。これは近藤の希望です。
これは深刻な問題ですね。我が家の周辺でもバスの便数が減ってしまいました。ひとつの要因は人手不足ですが、解消には時間がかかりそうですが、どんな仕事でも誇りをもって働くことができる社会の構築が大切なのではないかと思います。
モビリティーに関しては様々な選択肢が出てきました。ハードウエアだけでなく、ソフト的な対策でも対応できるのではないか。国内に先進事例がありますので調べるとおもしろいと思います。
これは重要なアイデアですね。日本では郊外に大型商業施設ができて、中心街が衰退するという事例がたくさんあります。一方、諸外国、とくにドイツでは街の中心から自動車を排除して、人が歩いて楽しめる「コミュニティ空間」を形成し、様々な世代の人々がゆったりと過ごすことができる街ができています。それでいて都市の活性は保たれている。日本でもこのような都市計画はできないものか。
日本ではコンパクトシティー構想がこれに近いかも知れません。駅の周辺に機能を集約化し、高齢者も徒歩で様々な施設を利用することができる。郊外には若い世代が緑に囲まれたゆったりとした住宅で暮らすことができる。子供が独立し、老いたら街の中心部に移住することもできます。このような構想は都市計画・農村計画分野で検討され、いくつかの施策があるので調べてみるとおもしろいと思います。トラムを中心として郊外と都心を結ぶ富山市や宇都宮市の事例で、どのような構想に基づいているのか、調べて見てください。
具体的な地名が出てきました。ニュータウンとは高度経済成長期に都市へ通勤する人々のために郊外に建設された住宅団地です。建設から大分経ち、住民の高齢化も進み、様々な問題が顕在化してきました。多摩ニュータウンや千里ニュータウンが有名ですが、何が問題となり、どのような解決方法が試みられているのか、参考になると思います。
千葉ニュータウンは良いところですね。都心に直結し、都市域の外側には良好な農村的景観が残っています。周辺の里山を愛でるニュータウンの住民も多く、都市と郊外の良好な関係が構築されていると思われます。ただし、問題も多いようですね。現場に入り込み、問題の詳細と背後にある事情を探り、可能な策を講じていく必要があります。その際に、どのような街づくりをめざしているのか、具体的な理念を明確にして、計画を考えてみてください。
---
---
---
能登半島地震(2024年1月1日)
元日に発生した能登半島地震に関する諸機関による情報は直ちにWEB上で共有されます。大きな災害や事故が起きた時は、わがこと化して、状況の理解に努めてください。それが生きる力を育みます。そして、被災した方々に対するエンパシーも醸成され、社会を良くする力になると思います。
能登半島豪雨(2024年9月21日)
地震で大きな被害を被った能登半島で大規模な水害、斜面災害が発生しました。人々の苦境は想像するにあまりあります。能登半島で暮らす“ひと”の立場で現状や未来を考えてください。 私たちは安全な場所にいて、様々な情報に接することができますが、それらの情報がどのような立場で、誰に向けて発信されたものか、考えることは災害の現実の理解に役立つと思います。それによって、災害における自分の役割を意識することができるようになると思います。前提は、苦しんでいる人々が苦しみから解放されること、どのような地域を創るか、地域をサポートする政府の役割は何か、自分の考え方を持つことです。地理学の知識、経験が役に立つと思います。
初回はオンデマンド講義とのことです。まず、教科書「みわたす・つなげる人文地理学」の第1章をじっくり読んでください。高校までの地理は指導要領が決められており、どちらかといえば受動型の授業でした(アクティブラーニングは重視されています)。大学の地理はこの世のあらゆる事象を扱います。この世(すなわち、人と自然の関係する外部である“環境”)を構成するあらゆる要素、要因と関係性を見抜く力を養います。地理学を通じて多様な視座と視点、幅広い視野を身につけるように心がけてください。
地理学では様々な地図を使って地域の理解を深めます。WEBで使えるページが充実していますので、紹介します。活用してください。たくさんありますが、少しずつ追加していきます。
様々な主題図を画面上で重ねて表示できます。国土地理院では主題図情報、災害情報や、地理学教育支援サイトが充実していますので参考にしてください。
旧版地形図(明治以降に作成された地形図で、改訂によって旧版となった地形図)と現在の地形図を並べて表示できます。過去の土地利用は土地の性質を表し,災害を予見することができます。
自治体に作成が義務づけられているハザードマップのポータルサイトです。「重ねるハザードマップ」は情報量が豊富になってきました。
![]() 参考資料
参考資料
小林信一氏の上記の論文は考えさせると思います。もとになった、オルテガの「大衆の反逆」は訳本が2種類出ています。ひとつは寺田和夫訳(中央公論社、2002年)、もう一つは佐々木孝訳(岩波文庫、2020年)。佐々木訳の帯に書かれている文章を再掲します。「自分たちの生活が誰によって創られ、維持されているかを想像することなく、自らに課せられた使命や義務を考えようとしないとき、私たちは誰も『満足しきったお坊ちゃん』である。オルテガの本を読み、これを『新鮮な自己批判の書』として読む理由はそこにある。」(本書解説より)。
![]() 過疎の話をしました。参考文献を紹介します。田舎はけっこう強いのだ!
過疎の話をしました。参考文献を紹介します。田舎はけっこう強いのだ!
![]() モンサント社のGM菜種の話をしました。事実関係は下記の農研機構の記事を参考にしてください。その後のモンサントはどうなったか。WEBで検索するとたくさんの記事が出てきます。正しい情報を自分で探してください。
モンサント社のGM菜種の話をしました。事実関係は下記の農研機構の記事を参考にしてください。その後のモンサントはどうなったか。WEBで検索するとたくさんの記事が出てきます。正しい情報を自分で探してください。
![]() 人口統計については、まずは下記の総務省統計局の人口推計のページを参考にしましょう。都道府県、市町村の人口データはそれぞれのホームページでみつけることができます。世界の統計は下記のページから検索してください。
人口統計については、まずは下記の総務省統計局の人口推計のページを参考にしましょう。都道府県、市町村の人口データはそれぞれのホームページでみつけることができます。世界の統計は下記のページから検索してください。
![]() 参考資料
参考資料
日本のエネルギー問題に対する展望については省庁の文書のほかにも、民間のシンクタンクによるものをみつけることができる。ただ受け入れるだけではなく、背後にどのような思想(地球観、社会観、人間観、文明観、などなど)があるのか、見極めてほしいと思います。
日本の国土の長期展望について、国はどのように考えているのか。わがこと化して考えてほしい。これら以外にも、様々な分野(省庁)の基本計画等があるが、中には科学的根拠が提示されないまま、政策との整合性をとるための文章もある。そこを見抜く力を大学で身につけてほしい。
地球温暖化問題をどう捉えるか。 自分の考え方をもってほしいと思います。そのためには世界の現状、歴史的経緯だけでなく、思想、宗教、価値観等にも踏み込む必要があるのではないか。大学時代は視野を広げる(意識世界を拡大する)ための格好のチャンスだと思います。自ら学んでください。
![]() 参考資料
参考資料
二つの農業-食べるための農業と売るための農業-の起源、生成、展開を総覧し、21世紀の世界が依拠すべき基本構図を明らかにする。(カバーより)
日本の農業政策には二つの潮流があるように思います.ひとつは経済指向、都市指向、農業を工業と同一視する見方、いろいろな言い方ができますが、この記事もそんな立場からの意見だと思います。もう一つは地域、コミュニティー、自然との共生、地域づくりといった方向で、20世紀後半の成長志向の雰囲気に対するオルタナティブな考え方です。農水省の政策にも二つの考え方が混在しており、日本の将来を考える方々は進む方向性をしっかり峻別する力を養ってほしいと思います。
![]() 考えよう
考えよう
 京葉工業地帯の成立過程
京葉工業地帯の成立過程
千葉県の東京湾岸には京葉工業地帯が立地し、日本の高度経済成長に大きく貢献した。その背後で何があったのか。例えば<京葉工業地帯 埋め立て 漁業権> で検索してみよう。いくつかのページがヒットする。その内容から海辺に暮らす人々に何が起きたのか、想像することができるだろう。
![]() 田園都市構想
田園都市構想